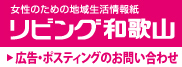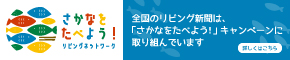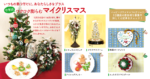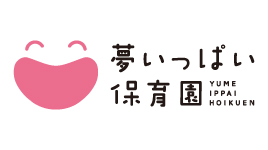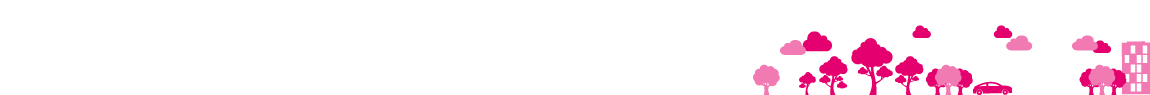和歌山県の手仕事を訪ねて
民藝100年の今を生きる
暮らしの中の道具に宿る「美」
- 2025/7/3
- フロント特集

1925(大正14)年、思想家・柳宗悦(むねよし)が、「民衆的工藝」を略し、「民藝」と主唱。暮らしの中にある生活道具に宿る美と、職人の手仕事の価値を見いだす民藝運動を始めました。それから100年、時代とともに変化しながらも受け継がれている和歌山県内の手仕事を紹介します。
日用品の美や職人の技術に着目
触れて、使ってみることが大切
「民藝」という言葉は、柳宗悦と陶芸家の濱田庄司、河井寛次郎らが、1925年に木喰上人(もくじきしょうにん、江戸時代の遊行僧)が彫り残した「木喰仏」の調査で、紀州の高野山方面を旅していたときに生まれたとされています。
「民藝運動が始まるまでは、日用品は“下手物(げてもの)”と呼ばれ、鑑賞の対象となるような美術品とは区別されていました。柳らは実用的な美しさや、それをつくる無名の職人の技術に着目。活動を通して、その価値を広めていきました」と話すのは、和歌山県文化遺産課・蘇理剛志さん。
民藝は使い込まれることを前提につくられており、陶磁器や染め物、木漆工、天然素材の細工物、郷土玩具(がんぐ)など多岐にわたります。近代化が進み、大量生産が進む現代社会においても、手仕事ならではの温かみや職人の個性が感じられる民藝は、世界からも注目されています。蘇理さんは「見るだけでなく、触れてみることが大切です。使うほどに良さが伝わってきます」と伝えます。
今号は県内の手仕事を紹介。ワークショップも開きます。手仕事に触れてみませんか!

作業場につるされた長さ約8mの染め物。獅子舞の幕は、獅子の毛を模した図柄など、地域によって少しずつ異なります
和歌山の祭りを彩る染め物
草木露をイメージ「雫染」考案
「うちは“祭り屋”とも呼ばれています」と話すのは、御坊市で3代続く老舗染め物店「そめみち染物旗店」の代表・染道祥博さん(写真)。毎年夏になると、同店の内装は一転。色鮮やかなのぼりや獅子舞の幕をはじめ、祭りの衣装一式が並びます。「地域によって色や柄などが異なり、それぞれの特色が際立つよう一枚一枚仕立てます」と説明します。

綿や麻の布地に、はけを使って塗ります。「赤一つとっても濃淡があり、立体感などの風合いが生まれます」と、染道さん
染色技法の中でも、同店が手掛けるのは「印染(しるしぞめ)」で、遠くからでも文字や絵柄がはっきりと分かるのが特徴。室町時代に始まり、江戸時代になると庶民の間で広まったとされています。家紋や屋号の印が入った、のぼり、旗、のれん、法被、手ぬぐいといった染め物は、日本のハレの日を彩るものとして継承されています。
印刷技術の進歩とともに、手染めの技法は特別なものと捉えられるようになりましたが、温かみのある風合いは、手作業だからこその魅力があります。染道さんは、染め物をもっと身近に感じてもらおうと、地元などで染め物体験のワークショップを開く他、動画やSNSを通して、その良さを発信し続けています。
染道さんは「印染はにじみは御法度なのですが」と前置きしつつ、約3年前には、ぼかし染めを取り入れた新しい技法「雫染」を独自考案。草木の露の雫をイメージし、染料の一滴で布地に奥行きや陰影を表現。ハンカチや祝儀袋、コースター、Tシャツなど、商品は多岐にわたります。染道さんは、「日々の暮らしの中に染め物がある、そんな風景をこれからもつくっていきたいです」と先を見据えています。

たなびく獅子の毛や花などをデザイン

雫染のハンカチ(左)と「御祝儀袋はんかち」
そめみち染物旗店
| 電話 | 0738(22)0915 |
|---|---|
| 住所 | 御坊市島644-3 |
| ホームページ | https://somemichi.com |
先人の思いを紡ぐシュロ製品
ブランド「Broom Craft」の誕生にも

穂が抜けにくい製法、三つ編みや斜めカットの意匠性などで特許を取得

シュロを編む職人
「職人が途絶えました。ほうき(シダ)を作れませんか?」という京都からの問い合わせが、深海産業の新たな挑戦の始まりでした。
古くから、シュロのほうきやたわしの産地として知られる海南市。長年にわたり、シュロ縄を取り扱ってきた同社は、不在となった職人の技をたどりながら、試作を重ねることに。事業部長の津村昂さんは「何としても復活させようと、見よう見まねで完成。結果、皆の発想を生かした新たな技法が誕生しました」と振り返ります。
経験を通し、同社は技術を受け継ぐことの大切さを改めて見つめ直し、「職人育成プロジェクト」に加えて、ブランド「Broom Craft」を立ち上げました。現在、男女6人の職人たちが中心となり、ほうきやブラシなどを製作。「以前のように、シュロが生活の一部になれば」と、先人たちの思いを丁寧に紡いでいます。

笑いが絶えない工房。全員が作業の全工程をマスターしている強みも。
深海産業
| 電話 | 073(487)2498 |
|---|---|
| 住所 | 海南市阪井1391-4 |
| ホームページ | https://fukami1178.jp |
紀州郷土玩具の「瓦猿」と「寝牛」
ずっしり、ひんやり心地よい手触り

年代別の瓦猿は表情が異なってあいきょうあり(上)。寝牛も人気(下)

瓦を流し込む石こうの専用型
かつて和歌山市の田中町は、瓦町と呼ばれ、瓦職人の町として栄えました。「江戸時代に瓦職人の内職として始まったのが、いぶし銀を焼き付けた瓦猿と寝牛です」と話すのは、元瓦問屋「野上家」4代目・野上泰司郎さん。
紀州郷土玩具として知られる一方、瓦猿は安産祈願や子授け、寝牛は草(はれ物)を食べさせ病気平ゆを願い、神社に奉納する習わしも。「手の中に収まるサイズですが、ずっしりとしていて、肌に触れるとひんやりと心地よいでしょ」と笑顔を見せます。現在、製造に関わっているのは野上家だけ。地元の文化が途絶えないように守り続けています。

べんがら(赤色顔料)で顔と桃を数回重ね塗りします
野上家代表 野上泰司郎さん
「リビングを見た」と伝えると、製作現場が見学可能。電話で要予約
野上家
| 電話 | 073(425)1988 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山市田中町4-112 |
| ホームページ | https://kawarazaru.com |
鮮やかな色と繊細な幾何学模様
糸色1つで個性が出る「てまり」

トンボと波、アサガオ、ネコ、フクロウ(左上から時計回り)。手の平サイズ、両手で抱える大作などさまざま

平安時代が起源とされる「てまり」。江戸時代には、各藩の姫の遊び道具として作られ、次第に庶民の間に浸透。模様や配色、技法など、各地で発展を遂げました。
てまりは、綿やもみ殻などで作った球体を等分割し、糸をかがることで、花や伝統柄など幾何学的な模様を生み出します。日本てまりの会教授・山鹿和子さんは「色や模様、素材など、自由度が高いのが特徴です。糸色一つ違うだけで雰囲気が変わり、アイデアと工夫次第で伝統的にも現代的にもなります」と、その良さを伝えます。
近年はアクセサリーやチャームなど暮らしに寄り添いながら、てまりの魅力が広まっています。

1針1針糸を差します
日本てまりの会教授、リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室講師 山鹿和子さん
夏休み企画
親子、中学生以上は1人参加もOK!手仕事ワークショップ
対象:小学生以上
お申し込みはこちら
7月27日(日)午後1時~2時ごろ
そめみち染物旗店
型染めマイバッグ作り

他にも図柄があるよ
用意された染型の中から好みの柄と染料の色を選び、自分だけのバッグを手作りします。染め物にまつわる話も併せて楽しめます。
※染料は服に付くと取れないので、汚れてもよい服装で参加を
| 定員 | 4人 |
|---|---|
| 材料費 | 2000円 |
| 場所 | そめみち染物旗店(御坊市島644-3) |
7月29日(火)午後1時〜3時ごろ
紀州和歌山のてまり
幾何学模様をかがろう

7色の厄よけてまり 色の選択もOK
一見、複雑な模様も、基本が分かれば、ぐっと身近に感じられ、楽しく作ることができます。色とりどりの糸を使って、てまり作りを体験しましょう。
| 定員 | 5人 |
|---|---|
| 材料費 | 2000円 |
| 場所 | リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室(和歌山市本町2-1 フォルテワジマ4階) |
8月7日(木)午前10時〜正午ごろ
深海産業
シュロの手ぼうき作り

力がなくても職人がサポート
持ち手とひも部分の革を選び、下準備されたシュロの手ぼうきに銅線を巻いて仕上げます。柔らかな掃き心地。日々の掃除道具を自分の手で作りましょう。
| 定員 | 20人 |
|---|---|
| 材料費 | 手ぼうき1500円 |
| 場所 | リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室(和歌山市本町2-1 フォルテワジマ4階) |
■メールで申し込み
件名に希望するワークショップ名「染め物」、または「てまり」「シュロ手ぼうき」のどれかを入力
※小学生は保護者1人の同伴が必要
本文には①参加したいワークショップ名(件名と同じ)②参加者の氏名と年齢(複数で参加する場合は参加者全員の名前と年齢)③代表者の連絡先電話番号を明記し、下記アドレスまで
【メールアドレス】living@waila.or.jp
※メールで申し込むのが難しい場合は、下記、和歌山リビング新聞社に電話してください
【締め切り】7月16日(水)午後5時まで
応募多数の場合は抽選。当選者にだけ、7月18日(金)にメールまたは電話で連絡します
※メールや電話で連絡が取れない場合は、参加できません
| 問い合わせ | 073(428)0281 和歌山リビング新聞社 (祝日除く月~金曜午前9時半~12時、午後1時~6時半) |
|---|