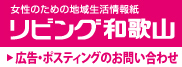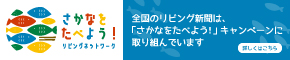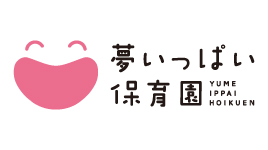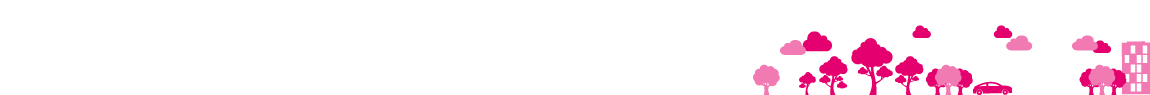語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶
- 2025/8/7
- フロント特集

1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少なくなる中、その声と平和への願いをどう未来に残すかが問われています。戦争と平和について考えるきっかけに。
空襲で和歌山市街地が火の海
約1100人以上が犠牲に
太平洋戦争は、石油や鉄鉱石などの資源を確保するために中国や東南アジアへ進出した日本が、米・英国など連合国と対立したことから始まりました。1941(昭和16)年12月、日本軍のハワイの真珠湾攻撃をきっかけに、戦争が勃発。やがて本土空襲が激化し、攻撃は中心都市から地方へと拡大しました。
1945(昭和20)年7月9日、深夜から翌未明にかけて行われた和歌山大空襲では、アメリカ軍のB29爆撃機108機が和歌山市を襲撃。約800トンもの焼夷弾(しょういだん)によって町は火の海となり、市街地の大半と和歌山城の天守閣が焼失し、1100人以上が犠牲となりました。
汀公園にある戦災殉難者供養塔の碑文には「戦争の惨虐(ざんぎゃく)また説くに忍びない~中省略~平和の悲願達成を祈るものである」と刻まれ、当時の悲しみと平和への願いを伝えています。

和歌山城北側の和歌山商工会議所屋上から東の方向を撮影。写真手前の建物は和歌山警察署、その隣が綿ネル組合の建物。元の和歌山国民学校の敷地は空地となり、その奥東側のビルが高島屋百貨店とみられます(和歌山市蔵)
戦争体験者の声を後世へ残す
10年間で約170人の証言

和歌山大空襲絵巻物。当時、中学2年生の男子学生が描いたもの(和歌山市立博物館蔵)
「火が迫り、熱い」「恐怖」「逃げるのに必死」「(助かったのは)運が良かった」―。和歌山市の空襲を体験した人たちの声を後世に伝え残そうと、和歌山市立博物館は、2015(平成27)年から体験談の記録活動を続けています。その中心となっているのが元副館長の髙橋克伸さん(写真)。

「声を集められる限り、続けていきます」と話す髙橋克伸さん
活動は髙橋さんが学芸員として勤務していたとき、歴史資料収集の一環として開始。同市内で空襲体験した人々の証言をボイスレコーダーなどで記録し、2年ごとに要約したものをパネルで展示しています。退職した後も活動を続け、10年間で約170人の証言を集めてきました。
髙橋さんによると、証言には戦争の悲惨さを物語るものが多く、空襲の日、翌日も学校があると思い教科書を持って逃げた子どもや、乳児を背負ったまま用水路に上半身をつけたまま亡くなっていた女性の姿を目撃したという話も。「話を聞いていると、想像もできないような状況が起こっていたことを痛感します。中東などで起きている戦争も同じ。今この時間も世界のどこかで逃げまどっている人たちがいることを思わずにはいられません」と伝えます。
同館で8月17日(日)までパネル展が開かれています。髙橋さんは「80年前に和歌山市で起こった出来事を知り、考える機会になれば」と話しています(下記参照)。
和歌山市立博物館 ホール展示
戦後80年和歌山大空襲の記憶
8月17日まで開催中

B29爆撃機のラジエーター(奥)と機関銃(手前)
和歌山大空襲の体験者約170人から聞き取った証言をパネルで紹介。爆撃機の一部など、関連資料も展示されています。
和歌山市立博物館(同市湊本町)
| 開催時間 | 午前9時~午後5時(入館4時半まで) ※ホール展示は観覧無料 |
|---|---|
| 休業日 | 月曜 |
| 問い合わせ | 073(423)0003 |
つなぐ、戦争体験と声
和歌山大空襲を体験した2人と、沖縄県のガマで遺骨収集ボランティアを行っている和歌山県立医科大学の学生の声を伝えます。
避難していた壕に焼夷弾が投下
母が私をおんぶして水田へ

山本文子さん(88歳) 当時8歳
目の前が煙で黄色に染まる
大空襲の日、私は和歌山市の小松原通りの自宅から、母が信仰していた栄谷の神社に、母と6歳上の姉と3人で避難していました。屋敷には大勢の人が集まっていました。夜、空襲警報が発令され、私たちは敷地内の防空壕に逃げ込みました。
途中、姉と母がトイレから戻り、壕に入ろうとした瞬間、壕に焼夷弾が落ちてきました。目の前が煙で黄色に染まり、皆は外へ飛び出し、私は一人逃げ遅れました。
壕から出てきた私を見た姉が「文子、いたで」と叫び、母が私をおんぶして境内にある田んぼへ走りました。田んぼには田植えのための水が張られていて、焼夷弾が次々と落ちてくる中、皆が田んぼの中を逃げ回りました。私は母に「熱いよ、水飲みたい」と言い、母は手ですくった水を私に飲ませてくれました。そして、やけどをした顔や手、足を水に浸してくれました。
翌朝、兵隊さんが「この子、えらいやけどや」と言い、赤チンを塗ってくれました。迎えに来た父は私を見て「えらいこっちゃ」と驚きました。
その後、治療のために母の実家がある桃山町へ汽車で行くことに。和歌山駅(現紀和駅)は人であふれ、汽車を待つ間にも艦載機が急降下してきたため、皆が地面に伏せました。桃山に到着すると、親類がリヤカーを用意して待っていて、ござと布団を敷いた上に私を寝かせ、病院まで運んでくれました。でも病院に薬はなく、医者は父に「食用油を1升探してきてください」と頼みました。父は親類宅を回り、集めてくれたそうです。
私はワセリンを食用油で練ったものを体中に塗られました。母は、うじ虫がわかないよう、そして少しでもやけどの痕が残らないようにと、指1本ずつにも丁寧に塗ってくれました。私は40日ほど寝たままで過ごしました。退院時、ひょこひょこ歩くと、皆が手をたたいて喜んでくれました。
終戦の日はとてもいい天気でした。ラジオの前に集まって玉音放送を聞いたことを今でもはっきりと覚えています。
私は、多くの人に助けられ、今こうして生きていることに感謝し、日々過ごしています。世界各地で起こっている戦争の情報を見聞きする度に心が痛みます。戦争は絶対あってはいけません。
焼夷弾が空中でばらけ落ちる
光景や臭いを今でも思い出す

佐古善三郎さん(92歳) 当時12歳
暗闇の中、燃え上がる和歌山城
当時、私は和歌山市南休賀町に住んでいました。戦中、民家は目立たないよう壁板を黒く塗っていました。また、国民学校では竹やりで戦う訓練をし、家に帰れば火災時に備えてバケツリレーの訓練をしていました。子ども心に戦況が悪くなっていくのを感じていたものの、今振り返ると、一種のマインドコントロールだったと思います。
7月9日は、宵のうちから警報が鳴り、避難しました。しかし、B29編隊が南下したため、すぐに解除されました。午後11時ごろ、再び警報が鳴り、しばらくして御膳松の方から火の手が上がりました。空を見上げると、焼夷弾の塊が空中でばらばらになり、40個ほどの爆弾が降り注ぐ様子がはっきり見えました。紀の川があるから、こちらまでは火が移らないだろう、と考えながらも不安でいっぱいでした。
私たち一家は三木町の橋の下に避難しました。炎が近づいてきて、丸正百貨店の一角から火花が立つのを目撃しました。後で聞けば、焼夷弾が落ちたとのことでした。やがて、和歌山城が燃え出しました。暗闇の中、城が真っ赤に染まっていく光景は、今でも目に焼き付いています。
子どもは皆、布団をかぶり、その上から大人たちが川の水をかけ、やけどをしないように守ってくれました。橋のたもとにあった薬品庫が燃え、私たちは手ぬぐいを水に浸し、口に当てて煙を防ぎました。一晩が、どれほど長く感じたことか―。
翌朝、川には焼け焦げた遺体がたくさん浮いてました。日が昇り、橋の上に出てみると、辺り一帯は焼け野原。乳児を背負った女性が焼けて倒れていたのを今でも忘れることができません。その時の光景や臭いなどは、体験した者でないと分からないでしょう。
戦後はしばらくの間、下津町にある母の実家に妹2人と疎開しました。午前4時半に起床し、3人分の弁当を作って学校へ。帰宅すると、田畑の手伝いをするなど、本当によく働きました。
私は九死に一生を得ました。神仏が守ってくれたのだと、命のありがたさに、ただただ感謝するばかりです。戦争はみじめなもの。犠牲になるのは国民です。絶対に戦争はなくさなければなりません。二度と同じ過ちを繰り返さないためにも。
医大生が沖縄県のガマへ
遺骨や遺品を家族のもとに
和歌山県立医科大学 医学部4年 小鮒亜裕美さん
沖縄戦でガマ(自然洞穴)は、住民の避難場所などとして利用されました。戦没者の遺骨や遺品を家族のもとに届けるため、ボランティアらによる遺骨収集の活動が続けられています。

遺骨の鑑定作業を行う様子。右端が小鮒さん
(写真提供=日本法医病理学会)
ガマでの遺骨収集は8年前、沖縄のボランティア団体から「個人識別やDNA鑑定など専門的な協力を」と、日本法医病理学会に依頼があったことがきっかけと聞いています。和歌山県立医科大学の法医学講座の近藤稔和教授が同学会の理事長ということもあり、本学の学生にも声がかかり、私は4年前から毎年参加しています。
活動は全国の法医学の医師や医学生など、約30人で2日間行います。初日はガマとその周辺で遺骨などを収集し、翌日、鑑定作業にあたります。ガマの内部は温度と湿度が高く、酸素も薄く感じられます。決していい環境とはいえず、避難していた人々がどれほど過酷な状況にあったのか、思いを巡らせます。
堆積した土砂の中から手掘りで探す
 1つのエリアにいくつかのガマが隣接しています。私たちはガマの中に入って堆積した土砂の中から、遺骨を探します。ただ、長い年月がたっているため、10㎝以上ものかたい土砂をかき分けないと出てこないことも多いです。初めて参加したとき、スコップを使用しましたが、遺骨を傷つけないためにも翌年からは手で堀るようにしました。
1つのエリアにいくつかのガマが隣接しています。私たちはガマの中に入って堆積した土砂の中から、遺骨を探します。ただ、長い年月がたっているため、10㎝以上ものかたい土砂をかき分けないと出てこないことも多いです。初めて参加したとき、スコップを使用しましたが、遺骨を傷つけないためにも翌年からは手で堀るようにしました。
遺骨なのか木や岩なのか判別の難しい破片が見つかる年もあれば、DNA鑑定が可能な遺骨が全く見つからない年もあります。また、ある年には焼けたような遺骨の一部を発見したこともありました。現地のボランティアの人によると、ガマに投げ込まれた手りゅう弾の影響ということでした。かんざしなど、名前が書かれた遺品も多く出てきます。DNA鑑定ができなくても、身元を特定する貴重な手がかりになるため、見逃さないことが大事だと感じています。
活動は年1回ですが、微力ながら専門性を生かして一人でも多くの遺骨や遺品が家族のもとに戻ればと、今年も参加を決めました。遺骨に尊厳をもって接することは、将来、医療人としての心構えを学ぶ機会にもなっています。