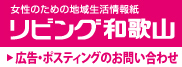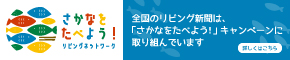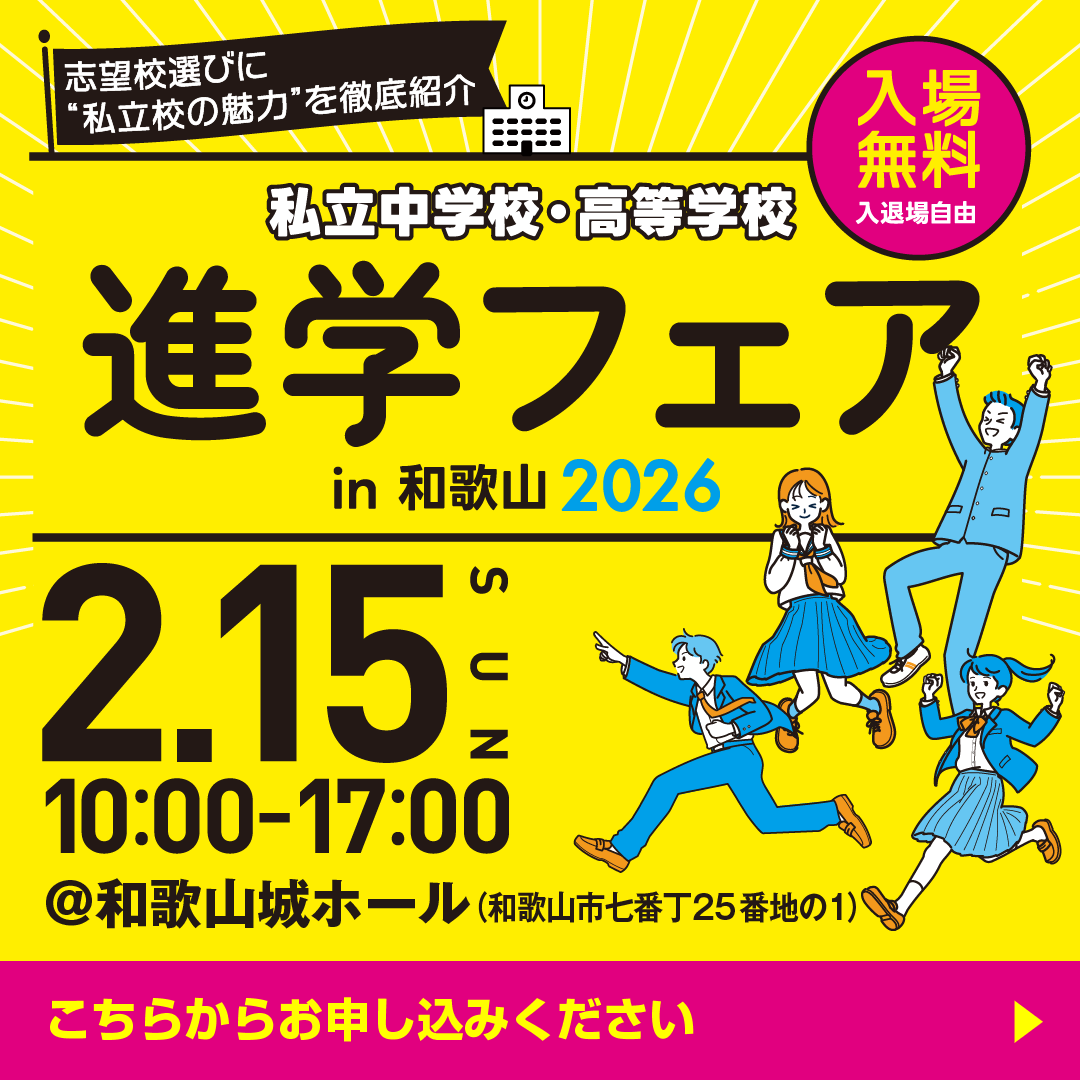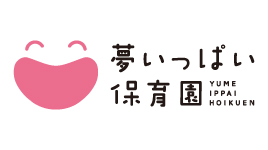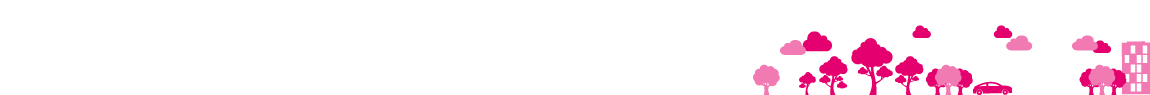音無茶の復活で地域経済の活性化を

左から九鬼宮司、倉谷さんとパートナーのジョーダンさん
法皇や上皇が行った熊野御幸。その際に茶木が本宮に持ち込まれ、栽培が始まった歴史と伝統のある音無茶ですが、近年は生産者の高齢化や後継者不足で、熊野本宮大社の新茶祭に供えられる以外、ほとんど作られなくなりました。「このままでは、青々しい茶畑が広がる本宮の風景と、音無茶という地域の文化がなくなる」と危機感を感じ、倉谷夏美さんは音無茶の復活プロジェクトを立ち上げました。
倉谷さんが祖父の茶畑を受け継いだのは5年前。農薬不使用・無化学肥料で栽培し、そのお茶はすっきりとした味わいで香りも爽やかと評判もよく「釜炒(い)り茶」という名称で販売してきました。そして今年、熊野本宮大社にその品質とこだわりを認められ、「音無茶」という名称を用いて販売できることになりました。

せん茶、紅茶、釜炒り茶。3種の音無茶
しかし、音無茶復活に向けて問題なのは、生産量が足りていないこと。「祖父の茶畑は約50歳、茶木の経済的な寿命も50年といわれ、年々収穫量も減少。増産のためには茶木の植え替えが必要ですが、それにはどうしても重機が必要なんです」と語る倉谷さん。また、熊野本宮大社の九鬼宮司と話す中で、「新茶祭を拡大し外国からも人を呼べる国際的なお祭りにしたい」という思いが一致。そのためにもお茶文化を守らなければと、費用を集めるためのクラウドファンディングを開始。わずか10日で初期目標に到達しましたが、現在はセカンドゴールを目指しています(12月25日まで)。
さらに本宮町と音無茶の魅力を国外に伝えるために、英語で案内するユーチューブチャンネルも開設しています(下記)。
| お問い合わせ | 090(7766)1046倉谷さん |
|---|---|
| クラウドファンディングはこちらから | https://for-good.net/project/1002532 |
| ユーチューブチャンネルはこちらから | https://www.youtube.com/@A-Journey-of-Rebirth |
関連キーワード