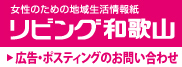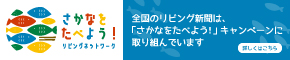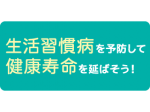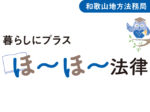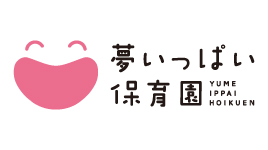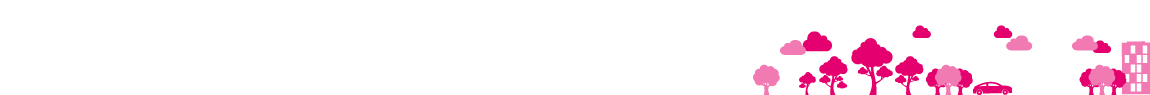私たちの日常生活は、「契約」に囲まれて成り立っています。例えば、“スーパーマーケットで食材や日用品などを購入する”“レンタルビデオ店で映画鑑賞用のDVDを借りる”“親から小遣いをもらう”“会社に就職する”、これらは全て「契約」です。つまり、契約とは、対価を払って人から物やサービスなどの提供を受けたり(売買・賃貸借契約など)、対価を払わずにお金や物を受け取ったり(贈与契約)、働いてお金をもらったり(雇用契約)することです。
契約は自分と相手の双方の意思表示が合致すると成立します。例えば、コンビニで弁当を買うとき、「この弁当を買います」という買い手(客)と、「この弁当を売ります」という売り手(店員)の意思表示が合致することで「売買契約」が成立します。また、当事者間の意思表示が合致した以上、原則、契約書を交わさない口約束であっても有効となります。
契約が成立すると、当事者には、それぞれ権利と義務が発生します。先の例でいうと、客は弁当の引き渡しを求める権利と代金を支払う義務が発生します。店員は代金の支払いを求める権利と弁当を引き渡す義務が発生します。
仮に、“代金を払ったのに商品を引き渡してもらえない”“商品を引き渡したのに代金を払ってもらえない”となったら、私たちは安心して経済活動を行うことができなくなります。一度契約が成立した以上、当事者にはそれぞれ契約した内容を互いに守る義務が生じます。契約内容と違うことをするのはもちろん、一方的な都合で契約を解消することも原則できません。これを「契約の拘束力」といいます。
このように、「契約」は私たちの生活と切っても切り離せないもので、暮らしを豊かにするために必要不可欠なものです。だからこそ、特別な理由がない限り、結んだ契約は誠実に守ることが大切です。何気ない日常の中にもたくさんの「契約」があることを意識してみると、これからの生活も少し違った見え方がするかもしれません。
(和歌山地方法務局総務課・森大輔)

総務課 監査専門官 森大輔さん
関連キーワード