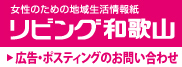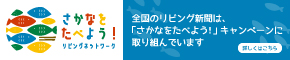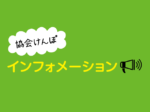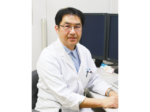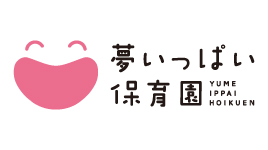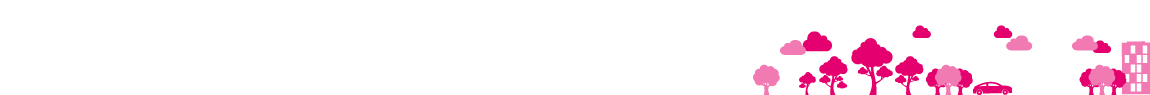和歌山県立医科大学で11月に、2025年度市民公開講座「子どものこころとからだに関する研修会」が開催。小児科学講座の徳原大介教授(写真)が登壇し、「子どもの腹痛」について、その要因や発症する背景、適切な対応などを解説しました。

子どもの腸管・肝臓の病気を専門とする徳原教授。自身も幼少時から腹痛に悩まされてきた、と話します
子どもの訴えに寄り添って共感を
「こころと神経発達に配慮が必要なこどもたちの腹痛に対処する」と題した教育講演で、徳原教授は「子どもの腹痛は、消化器系の病気から心理的要因まで、多様な原因が考えられます」と説明。全国で社会問題になっている小中高生の不登校に対しても、「腹痛は学校生活に大きく影響する症状の一つ」と指摘します。
腹痛は大きく分けて、「器質的疾患」と「機能性消化管疾患」が挙げられます。「器質的疾患とは、胃腸炎や潰瘍など臓器に異常があり、血液検査や内視鏡検査などで原因を見つけて治療すれば、症状が治まります」と解説。一方、機能性消化管疾患は検査で異常が見つからないのに、腹痛、下痢、便秘などの慢性的症状が続きます。「過敏性腸症候群や機能性ディスペプシア、起立性調節障害などが当たります」
機能性消化管疾患の対応として、「どんなときにどこが痛むのか。どれくらい日常生活が障害されているかを把握するために、丁寧な問診を行います」と、徳原教授。「食事や睡眠など生活習慣における改善点を見つけ、ストレス要因があれば、それを排除できたら非常に効果的」とも。加えて、「子どもの腹痛は家庭や学校で問題がある場合、心身症として捉えがち。『器質的疾患』が隠れていないかにも注意を配って診察します」と話します。
「家庭では子どもの痛みに共感し、腹痛が軽減するケア方法を見つけて実践して。症状が続くなら、最寄りの小児科や専門医に相談を」と、徳原教授は訴えます。神経発達の特性を持つ子は消化管障害の有病率が高く、また感覚過敏な面が影響するため、児童精神科が関わるケースもあります。
市民公開講座を主催した「小児成育医療支援室」では、子どもの発育や発達などの相談に、小児科医や公認心理師が応じてくれます。詳細は下記で。
関連キーワード